各種感染症への対応について(6月24日更新)
密を避けるため、ご喪家様と相談の上、一般会葬の皆様には、
参列をご遠慮頂く場合がございます。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。
また当社では、現在報道等で葬儀における感染症に対する緩和措置が
発表されておりますがこれまでと同様の対応をさせていただきます。
右下のリンクより当該ページへアクセスできます。
※実施期間 当面の間
各種感染症への対応について(6月24日更新)
密を避けるため、ご喪家様と相談の上、一般会葬の皆様には、参列をご遠慮頂く場合がございます。ご理解とご協力をお願い申し上げます。
また当社では、現在報道等で葬儀における感染症に対する緩和措置が発表されておりますが
これまでと同様の対応をさせていただきます。
※実施期間 当面の間
ご自身、ご家族、地域の「命と健康を守る」ためにどうかご理解の程お願い申し上げます。
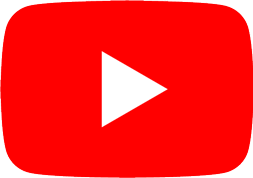 オンライン参列はこちら
オンライン参列はこちら




